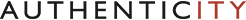2026/02/08 | Blog
文字通り価格がひとつに定まっていることにあり、事前の予算計画には適しているかもしれません。
基本的に追加料金が発生しないことは安心感にも繋がるでしょうし、ひいては信頼の向上にも一役を担っているのかもしれません。
既製品ではないソファにおいては、一般的に表皮材となるファブリック等をチョイスすることも可能なものがほとんどとなります。
当然のようにファブリックによって価格は様々ですので、ワンプライスとする場合は同価格帯のファブリックに限定することが望ましいものです。
その性質上汚れを気にされることも少なくなく、それに対応すべく一般的に機能性生地と言われるようなものを中心にラインナップされる場合もあるのですが、機能性に重きを置くと組成や織り方は限られることも多く、結果としてどれも同じような触り心地や表情に見えてしまうことも否定できません。
それでも安心して使用できることに越したことはないとの意識面も否定するものではないのですが、良い意味で少しでも肩の力を抜くことをお勧めしたいものです。
汚れにくいから安心とか、仮に汚れてもご自宅で洗うことも出来るので安心とか、それにより気兼ねなく使用できるメリットもあるとは思われるものの、その意識が先行し過ぎると本末転倒になってしまうことも考えられます。
汚したくないので極力使用を控えようとか、条件付きで使用しようとかの意識面がフッと湧いてくるかもしれません。
それゆえ一旦その意識面を外すことが望ましく、本当に気に入ったファブリックで張り上げたソファを気兼ねなく使用することより初めて得ることが出来る究極の寛ぎ感がソファ本来の重要な機能性だと考えています。
微妙な肌触り感も含めた豊富なランナップを揃えることにより必然的にワンプライス設定は難しくなるのですが、表皮材はソファにとってとても重要な要素のひとつとなることからも妥協することなく真のお気に入りを見つけることがお勧めです。
2026/01/27 | Blog
仕事柄、現調と言われる現地調査やその流れにて現場での打ち合わせを行うことも少なくありません。
現場合わせが必要になるいわゆる造作ものとは別に、現場にマッチする既存のデザイン性やサイズ感を確認する目的となることもあります。
場合によっては現場にマッチするデザインをゼロから起こすこともありますし、それがソファとなると先ずは試作品にて座り心地も試していただく必要もあります。
一般的に家庭用の場合は心地良い座り心地であることが絶対条件になるのですが、それがオフィス用途になると少しばかり違ってくることもあります。
先日はある会社の役員室用の一人掛けソファとして、先方様が気に入られた定番モデルをベースとして新たにデザインした試作品を送付にて評価会を行いました。
事前に図面では確認いただいていたものの、やはり現物にてデザイン性も含めて評価いただく工程を踏むことは必要不可欠と言っても過言ではありません。
デザイン性については基本的に任せていただくことになるのですが、座り心地はとても主観的なものともあり、腰掛けられた際の最初の反応を注視しながら細かなニュアンスも含めて感じとることになります。
役員室に設置されるソファですが社内打ち合わせのためだけに使用されるものではなく、他の会社様との商談にも使用されるとのことです。
その用途からもゆっくりと寛ぐスタイルは比較的少ないようで、むしろ姿勢良く腰掛けるスタイルに向いている方が良いとの評価をいただきました。
まさしく基本的な使用用途の問題であり、設計事務所を経由していることもあり直接的なヒアリングが充分ではなかったことを反省することになったのですが、今更ながら用途によっては座り心地を追求するだけでは不十分なことを再確認することになりました。
2026/01/17 | Blog
以前にも記したことがありますが、「デザインとは線のお遊びではない」と大学時代にお世話になった教授より言われた言葉が今でも鮮明によみがえります。
本格的にデザインを学び始める学生に対して投げかける言葉としてはとても適切だと思っていますし、プロのデザイナーになるための覚悟を持たせる趣旨もあったのだろうと感じています。
つまりプロとしてその仕事に就くことは生半可な意識では難しいことを最初に教えていただけたもので、その教授とはご縁もあり私生活においてもいろいろとお世話になったものです。
残念ながら数年前には他界されたのですが、デザインの基本を教えていただいたことに対する感謝の念は常に持ち続けています。
一方では、デザインの基本を一切学ぶことなく自らをデザイナーと称していろいろと発信されている方々も少なからず見られます。
そのような方々の共通の特徴としては、やはり線のお遊びが多いことを感じ取れます。
おそらくそれがデザインだと勘違いされているのでしょうし、新奇性や斬新性を演出するための手段として多用していることが推測できます。
結果としてとても稚拙なデザインに見えてしまいますし、人間が使用するものとしての機能性についても充分考慮されているとの印象も少ないものです。
一時的にでも消費者に受ければすべてよしとの考え方も一部ではあるとも思われますが、それはデザインの偏差値の問題だとも考えられ、結果として消費者のデザインに対する価値観アップの妨げになる部分も否定できないようにも感じています。
少なくともデザインは純粋美術ではないことからもその人の感性だけでは難しいと考えており、人が使用するものであればやはり人間工学についても多少なりとも学ぶ必要はあるのだろうと考えています。
2026/01/07 | Blog
例年同様の書き出しになるのですが、早いもので新年のご挨拶も今回で19回目となります。
これを機に過去18回分を一度に読み返すことも慣例化しているのですが、昨年は特に印象的なものとなり、心身ともに疲弊気味だった一昨年の自身を再確認することになりました。
何気ない日常が如何に大事なことかと思い知ることになり、ともかくも無事平穏に過ごすことを意識したものです。
一方では、日々の忙しさは変わることなく継続しており、周囲からも「もうそろそろ身体のことも考えないと…」とのアドバイスを受ける頻度も高くなった印象です。
もちろん年齢的なことを基準としたアドバイスだと受け取っており、ひとつの区切りとして大学の同級生となる友人からは久しぶりに皆で会わないか…との誘いも受けているのですが、休みが合わず難しい状況が続いています。
それゆえ皆には気を遣ってもらっているようで、自分たちは比較的調整しやすい環境になったため当方の都合を聞きたいとの内容です。
仕事的にも皆そのような年齢になっていることを再確認することになったのですが、気持ち的にも充分な余裕がなく積極的に行動出来ない自身が居ることも事実です。
このような状況を冷静に捉えると、日々の仕事にかこつけて精神的な余裕を意識的に生み出す努力を怠っていることが見えてきます。
結果として忙しい毎日を過ごすことが身に付いてしまったようで、このことは身体的にも精神的にも決して好ましいこととは考えにくいものです。
そのような環境下では良いアイデアも生まれにくいのかもしれませんので、今年においては良い意味で自身の時間をつくり出すことが出来るように意識していきたいと考えています
2025/12/27 | Blog
ある特定の国からの観光客は肌感として間違いなく少なくなっている印象です。
その背景をめぐってはいろいろな意見があることも承知していますが、個人的には日本としての毅然とした姿勢を貫くべきだろうと考えています。
一方では明らかな偏向報道とも受け取られるような批判的な内容も多く見られるもので、そのような報道を見聞きするたびにその意味合いについて疑問視することになります。
思想は様々ともありここではそれについて深く追求する趣旨はありませんが、これを機に日本人として少しばかり考える機会を設けることは決して間違いではないだろうとも感じています。
仮にある特定の国に依存し過ぎる部分があるとすれば、その関係性に何かあるとやはり影響も決して小さなものではないのでしょう。
依存度合いが高くなるほどリスクは大きくなると言うことでしょうし、依存度が高いと思われる国外でのモノづくりについて今一度考え直す必要はあるように感じています。
日本国内における総合的なモノづくりは世界トップレベルと言っても過言ではないでしょうし、そのベースには優秀な頭脳から生まれる機械開発にもあるのかもしれませんが、やはり日本人が生まれ持つ感性面が背景にあるだろうと考えています。
同じ動作を繰り返す優秀なロボットにおいても、その中には日本人の細かな感性が織り込まれているものと考えていますので、必然的にそこから生み出される製品にもその感性が練り込まれているものと考えています。
それゆえ日本製品は使用していてどこか心地良いと感じられるものとも考えていますので、やはり国内製造することのメリットは決して小さくないのだろうとの感覚です。
日本国内の製造コストは確かに高いとは思われますが、価格以上の価値を伝えることが可能な製品開発は必須なのだろうと感じています。