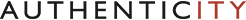写真との出会いは大学生時代までさかのぼります。
写真の原理を学ぶためにもピンホールカメラを自作しましたし、カメラを用いた授業ではフィルム現像から印画紙への焼き付けまで学ぶ機会に恵まれました。
カラーフィルムの現像は全暗での作業となることからも難易度が高くなることもありますが、純粋な写真を学ぶためにもモノクロフィルムを用いたものです。
それでも慣れないうちはその工程にて何度か失敗も経験しましたが、それだけにとても興味深く自身でもそれに必要な道具一式を買い揃えアパートの押入れを暗室代わりに作業していたことも思い出されます。(それらは現在も大切に保管しています)
現在のデジタル写真との大きな違いは、フィルムの場合は撮影枚数が限られることからも一枚一枚丁寧に撮影する必要があります。(「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」とはいきません)
既にその感覚は薄れてしまっていますが、このような一連のアナログ作業には相応に意味があったものと考えています。
カメラのファインダーを覗き込むところから始まり、印画紙への焼き付け作業が終わるまではどのような写真が撮れたか確認することは出来ません。
その点において現在のミラーレス一眼では撮影時におおよその仕上りも確認することが出来るようです。
既に一眼レフ機の時代は終了したものと思われますが、手に伝わるシャッターの僅かな振動や存在感のある音は何とも心地良いものがありますし、個人的には小さなファインダーを覗き込む撮影スタイルに大きな意味があるものと感じています。
液晶モニターでも確認することは出来るものの、レンズから入った光がレフレックスミラーを通して光学ファインダーに届けられる機構はカメラの原点のような気がします。
また、その小さなファインダーを覗き込み絵作りに集中することにより、味わいのある写真が生まれるものとも考えています。